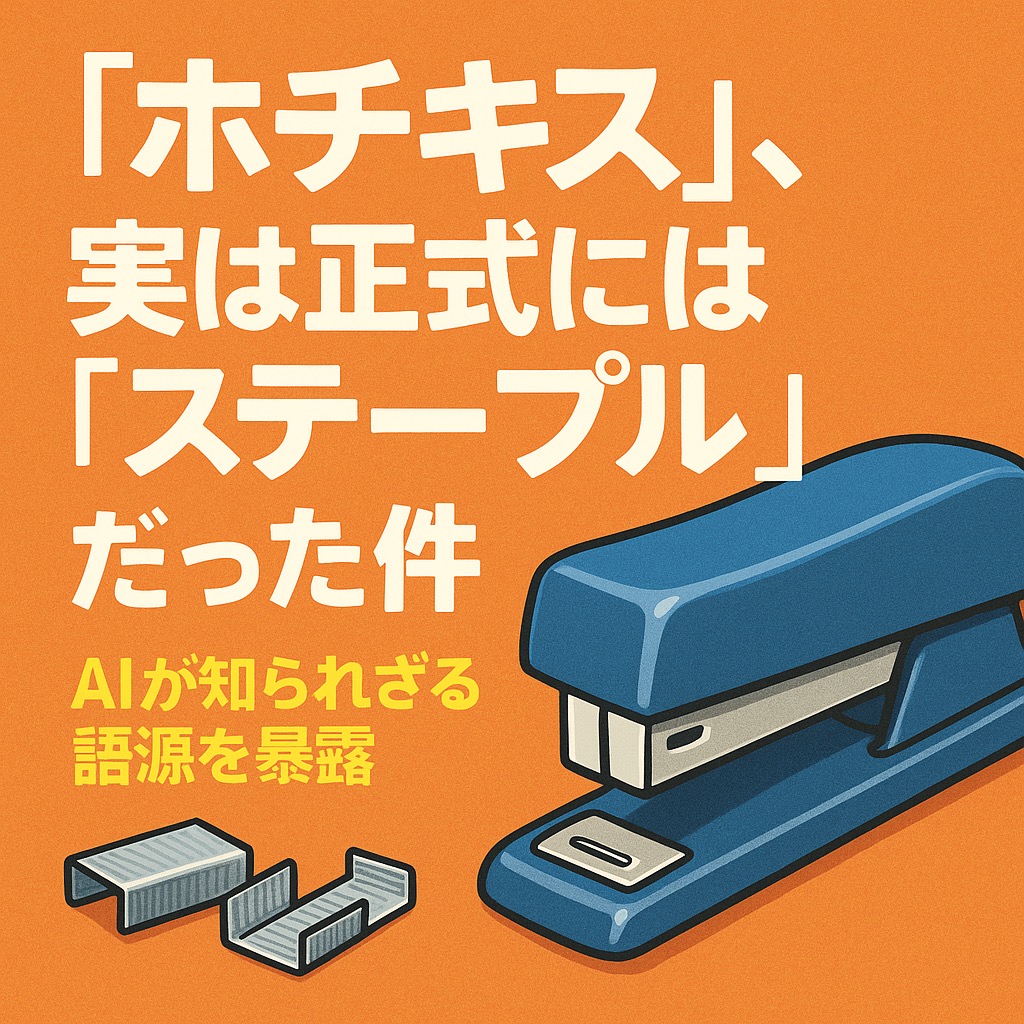目次
- ホチキスって実は“商品名”!?
- ステープルって何者なの?
- 海外では通じない「ホチキス」
- AIが語るホチキスの進化史
- 雑学:ホチキスの針の折り方にも意味がある!
- 結論:ホチキスでもステープラーでも、もう気にするな
1. ホチキスって実は“商品名”!?
あなたが普段「ホチキス」と呼んでいるアレ。正式名称、知ってますか?
そう、「ステープラー(Stapler)」が本名なんです。ホチキスとは、日本にこの道具を持ち込んだ最初のメーカー、E.H.ホッチキス社の商品名。つまり、「ホチキス」は一種の“固有名詞”だったのです。
例えるなら「ウォシュレット」や「セロテープ」みたいなもの。一般名称と化してるけど、本当はメーカー名。
2. ステープルって何者なの?
では「ステープル」って?
これは**針(芯)**のこと。そう、紙をまとめる金属の“あの部分”がステープル。つまり本来の分類で言えば、
- ステープラー(本体)
- ステープル(針)
なのに、なぜか日本ではまるっと「ホチキス」で統一されてしまったのです。
ちなみにステープルは、サイズにも規格があり「10号針」とか「11号針」とかって呼ばれています。知らなかった方、今日からマニアを名乗ってOK。
3. 海外では通じない「ホチキス」
ここで注意。外国で「ホチキス!」って言っても、キョトン顔されること必至です。
英語では堂々と「Stapler」。ちなみに「Staple」は動詞で「留める」という意味でも使われます。海外でプリントを提出するときに、
Could you staple this, please?
って言われても、「ホチキスして!」と訳せばOK。
4. AIが語るホチキスの進化史
AIによれば、ホチキスの歴史は意外と長いらしい。
「ホチキスの原型は18世紀フランス。ルイ15世の時代に書類を美しく留めるための装飾留め具が使用されていました。」
おお、さすが王様。紙を束ねるのにも美意識。
その後、19世紀後半に現在のホチキスに近い形が誕生し、やがて日本には明治時代に輸入。それを「ホッチキス」と名付けて販売したのがはじまりだったわけです。
5. 雑学:ホチキスの針の折り方にも意味がある!
知ってました?ホチキスの針、実は折り方が2種類あるんです。
- 内側に折る(標準):しっかり留めるとき用
- 外側に折る(仮止め):後で外すことを想定した留め方
多くのホチキスには、針の受け台が回転してこの切り替えが可能になっているモデルもあるので、ぜひ確認してみてください。「おおっ、知らなかった!」って感動するかも。
6. 結論:ホチキスでもステープラーでも、もう気にするな
ということで――
「ホチキスって正式名称じゃないの?」と驚いた方、安心してください。
日常会話では「ホチキス」で通じます。でも知識として「ステープラー」が本名、「ステープル」は針、と覚えておくと、どこかでドヤ顔できます。
AI曰く、
「名称の違いにこだわるより、紙をしっかり留めることに集中してください」
とのこと。うん、真顔で言うあたり、やっぱりAIは融通が利かないけど、ちょっと笑える。
明日、同僚との雑談でドヤってください。
「知ってた?ホチキスって実は商品名なんだよ」って。
会話のきっかけにどうぞ!