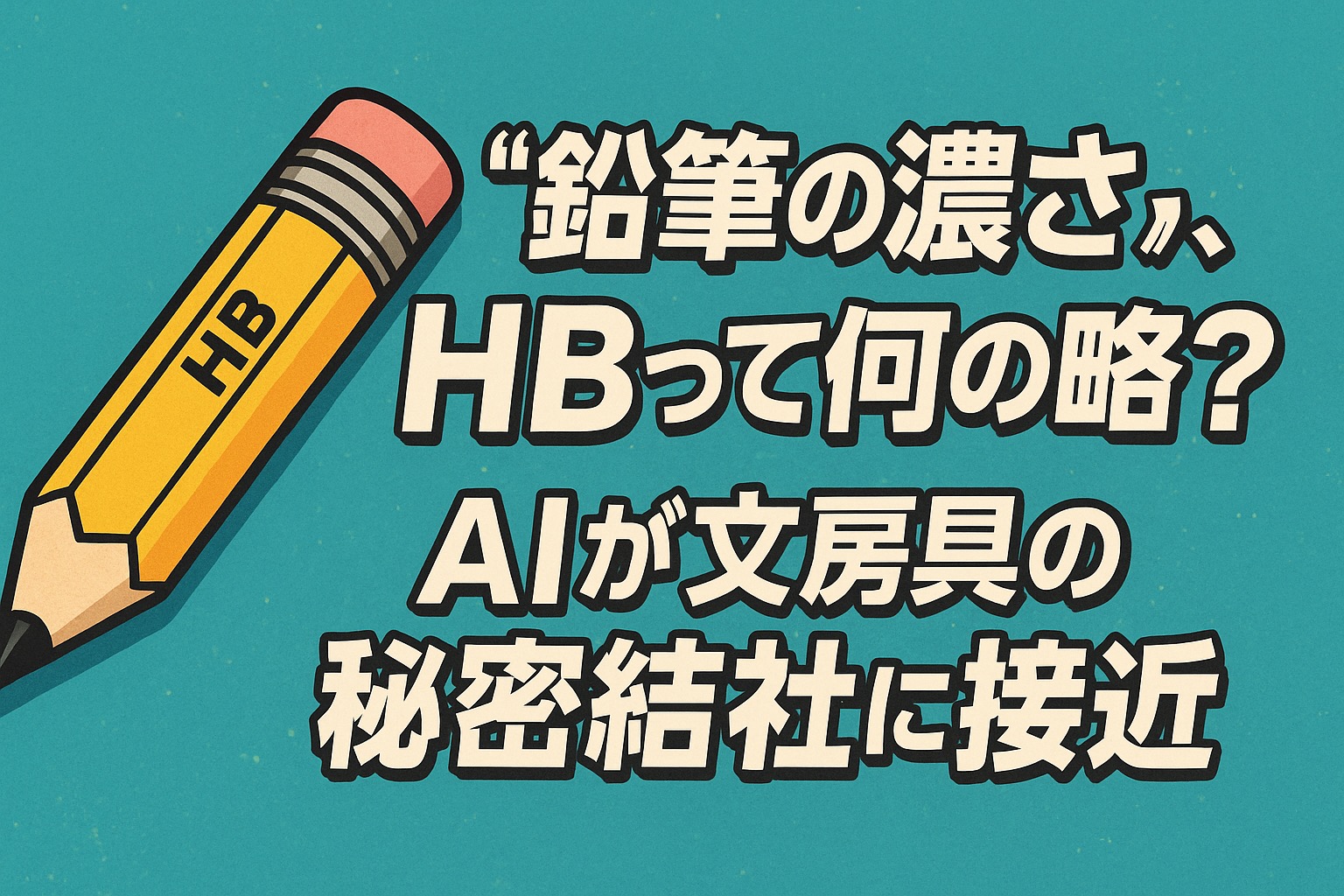→ Hard & Black。つまり“カタイくろ”。なんかかわいい。
目次
- HBって、ただの記号じゃなかった!?
- 知られざる文房具の“濃淡コード”
- 日本人がHBを好む深いワケ
- 海外ではHBは使わない!?
- 【オチ】文房具の世界は奥深く、意外と哲学的
HBって、ただの記号じゃなかった!?
突然ですが、あなたの筆箱の中に1本くらい、HBの鉛筆ってありませんか?
そしてこう思っていませんか?
「HBって…なんか真ん中っぽいよね」
はい、たしかにHBは“ちょうどいい濃さ”の代名詞みたいな存在。でも実はこの「HB」、「Hard(硬い)」と「Black(黒い)」の頭文字だったのです!
つまりHB=“カタイくろ”。
…なんかポケモンにいそうな名前ですよね。
しかもその命名、19世紀から続いている“由緒ある略称”なんです。
知られざる文房具の“濃淡コード”
鉛筆の世界では、「H(Hard)」と「B(Black)」の組み合わせで濃さを表現しています。
- Hの数が増えると薄くて硬い(例:2H、4H)
- Bの数が増えると濃くて柔らかい(例:2B、6B)
間をとってHBやF(Firm:HBよりちょい硬い)なども存在します。
ちなみに、日本の文房具屋で「10Hの鉛筆ありますか?」と聞くと、だいたい驚かれます。
なぜなら、10Hは石を削れるレベルの硬さだからです(もはや鉛筆界の武器)。
日本人がHBを好む深いワケ
では、なぜ我々日本人は“HB信者”なのでしょうか?
その秘密は「学校教育」にありました。
日本の小学校では「鉛筆=HB」がデフォルト。
硬すぎず、濃すぎず、**ちょうどいい“国民的バランス”**を誇ります。まさに文房具界の「白米」。
しかも、書道の筆圧練習にも応用できる万能選手。日本人がHBを選ぶのは、もはや文化的本能なのです。
海外ではHBは使わない!?
しかしこのHB、実は世界共通ではありません。
アメリカやヨーロッパでは、数字で硬さを表す「#2 pencil」などが主流。
#2がちょうど日本のHBに相当しますが、見た目も違えば感覚も違う。
さらに面白いのが、ドイツの技術者たちはB系を多用する傾向があること。
設計図を描くときには「黒くはっきり」が正義らしいのです。
文房具にも、お国柄がにじむんですね。
【オチ】文房具の世界は奥深く、意外と哲学的
HBが「Hard & Black」だと知ったとき、
ふと筆者は「じゃあ、人生におけるHBってなんだろう…」と哲学モードに入りました。
- 厳しさ(Hard)と情熱(Black)のバランスが人生の鍵なのか?
- それとも、薄すぎず濃すぎず、周りに馴染む“中庸”こそがベストなのか?
文房具ひとつから、ここまで妄想が広がるってすごくないですか?
今日からあなたも、鉛筆を手に取るたびにちょっとした雑学王として注目されるかも。
まとめ:HBとは「硬さ」と「濃さ」の中間地点。
だけど、そこには歴史と文化と哲学が詰まっていたのです。
次に鉛筆を削るとき、きっとあなたは「HBくん」に親しみを覚えるはず。